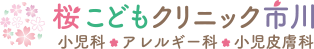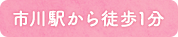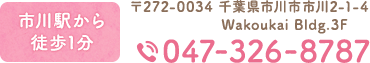花粉症治療について
 当院の診療では、まず患者さんのアレルギーの重症度を判定し、状態を把握してから薬剤の選択になります。
当院の診療では、まず患者さんのアレルギーの重症度を判定し、状態を把握してから薬剤の選択になります。
薬剤の選択は、内服、点鼻薬、点眼薬、眼瞼クリーム、テープ剤、ゾレア皮下注射、舌下免疫療法、と様々あります。
内服薬には、抗ヒスタミン薬、ロイコトリエン受容体拮抗薬、ステロイド薬、免疫調整薬など、複数の内服薬があります。
診療では、患者さんの状態を把握し、適切な薬剤を選んでいきます。
患者さん毎に症状の重症度や背景が異なりますので、オーダーメイドの治療に繋がっています。
また、アレルギー性鼻炎をお持ちの方は、気管支喘息やアトピー性皮膚炎、花粉果物アレルギー、口腔アレルギー症候群、接触性皮膚炎、結節性痒疹などが合併することがあり、それぞれ全身管理を行いながらの治療が必要になります。
アレルギー性鼻炎の舌下免疫療法を開始する場合には、全身状態を把握してから治療を開始する必要があります。
今まで当院以外で治療を受けられていた方の場合は、お薬手帳から内服薬や治療期間を精査して、どの薬剤がどの程度効果があったのかを把握する必要があります。また、お子さんの成長発達段階でどのようなアレルギーの経過を辿ってきているのか、全身状態を確認して、治療介入をしていきます。
お困りの症状は鼻水やくしゃみ、鼻閉だけでしょうか?春だけではなく、秋やその他の季節にも症状があるようでしたら、適切にお薬を使用していくことで、快適に過ごせる時間を多くできるよう、医療でサポートできればと考えています。
花粉症の件で質問が多い事項についてまとめましたので参考にしてください。
花粉症のお薬を飲んでも効かないですが、他に何かありますか?
 内服のタイミングは適切でしょうか?点眼薬の使用の仕方は大丈夫でしょうか?
内服のタイミングは適切でしょうか?点眼薬の使用の仕方は大丈夫でしょうか?
症状が出る前から、早めに粘膜の症状を抑えることで、快適に過ごせる時間が多くなります。
また、自宅に帰った時に外で付いてしまった花粉をなるべく持ち込まないことも大事です。日中の花粉対策についても相談して参りましょう。
最近はゾレア皮下注射を選択する方も増えてきていますので、様々な治療の中から選択しながら診療をすすめて参ります。
過去のアレルギー検査結果や、処方薬(お薬手帳) などがございましたら持参してください。
初期療法について
毎年3月・4月がお辛いスギ花粉症の方には、初期療法がおすすめです。
花粉症の飛散量が一番多い季節から内服薬を使うのではなく、12月末あるいは1月から内服薬や点鼻薬を定期的に使用していく方法です。
症状が辛くなる前から内服を始めることで、体の中のアレルギー反応が起こりにくくなる状態に整えていきます。
スギの舌下免疫療法はいつから開始できますか?
今まではスギの舌下免疫療法の初回の薬剤が少なかった影響から、希望の患者さんが開始できておりませんでした。
スギの舌下免疫療法の初回については例年5月ごろから11月まで開始できます。
一度、現在の全身状態を把握しますので、事前に受診してください。
ダニの舌下免疫療法については、いつでも開始可能ですので、花粉症かもしれないと思っていたら、ダニアレルギーだったということもあります。一度、診察を受けてください。
花粉症で咳が出ますか?
 アレルゲンがきっかけとなり咳嗽が出現することはありますが、アレルギーや気管支喘息についてのコントロールはどのような状態になっているか、一度確認させていただきます。
アレルゲンがきっかけとなり咳嗽が出現することはありますが、アレルギーや気管支喘息についてのコントロールはどのような状態になっているか、一度確認させていただきます。
また、咳嗽については、感染症が原因のこともありますので、咳の原因をひとつひとつ精査をして確認しながら、治療をすすめていけたらと思います。
大人も受診可能ですか?
アレルギー専門のクリニックとして、こどもだけでなく、大人の方も受診可能です。ご家族で受診する場合には、大人の方もWEB予約を活用してください。アレルギー検査や呼吸機能検査等も実施できます。また妊婦や授乳中の方の薬剤についても相談しながら治療薬を選択いたします。
当院は、日本アレルギー学会認定 アレルギー専門医が在籍しているクリニックです。
(https://www.ho.chiba-u.ac.jp/allergy/senmoni/index.html)
小児アレルギーエデュケーター(PAE:Pediatric Allergy Educator)やアレルギー疾患療養指導士(CAI:Clinical Allergy Instructors)も在籍しておりますので、お気軽に相談してください。
ゾレア®皮下注射はできますか?
 12歳以上の重症のスキ花粉症の患者さんに対して、2月~5月に抗lgE抗体薬(ゾレア®)の治療が選択肢として可能です。
12歳以上の重症のスキ花粉症の患者さんに対して、2月~5月に抗lgE抗体薬(ゾレア®)の治療が選択肢として可能です。
適応はそれぞれの患者さんにより異なりますので、一度受診してください。
受診したその日に接種できる薬剤ではありませんので、初回についてはスギ花粉症の重症度を把握させていただきます。
どの日に受診されても相談は可能ですが、より専門的な内容や説明をご希望の方は、最新の医師勤務表を参照して日本アレルギー学会認定 アレルギー専門医が勤務している日に受診をするようにしてください。