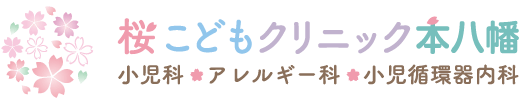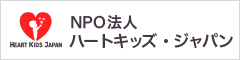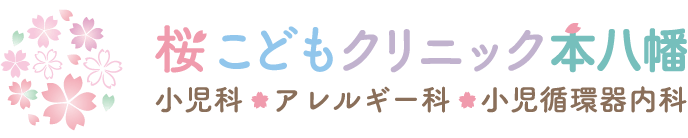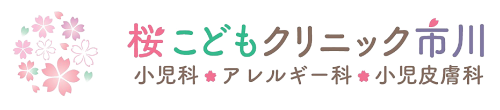生後2か月からのワクチンデビュー

日本では、ほとんどのワクチンを公費で受けられるため、ご負担なく接種が可能です。ワクチンは病気の発症や重症化を防ぐ大切な役割を持っていますが、種類によって接種回数や時期が異なるため、進め方に戸惑うご家族もいらっしゃいます。当院では、初めてワクチンを受けられるお子さまとご家族に、安心して接種していただけるようスケジュールを丁寧にご案内しております。
専門家の診察を受けつつ、これからの予防接種について一緒にスケジュールを考えていきましょう。
また、当院では、ワクチン接種の際に注射の痛みを少しでも和らげるために、接種はお母さんの抱っこで行っております。さらに、接種後にアイスノンで冷やしたり注射と反対の手にハンドグリッパーを握ってもらうなどの工夫により、注射部位の痛みを緩和できるように配慮しております。。
当院では、予防接種は一般診療と分けて専用の時間帯に実施しております。そのため、発熱や感染症を持つお子さまと同じ空間になることがなく、安心して接種を受けていただけます。
出生時の赤ちゃんはお母さんから免疫を受け取っていますが、その免疫は月齢が進むにつれて減少し、感染症にかかる可能性が高まります。感染症の中には命に関わるものもあるため、ワクチンでの予防が大切です。お子様が生後2か月を迎えたら、接種を始めましょう。
☆市川市以外に在住の方へのお知らせ
当院は「千葉県内定期予防接種相互乗り入れ制度」に申請していますので、船橋市在住や松戸市在住の方も予防接種が可能です。
〇船橋市のお知らせはこちら
https://www.city.funabashi.lg.jp/kodomo/kenkou/005/p002423.html
〇松戸市のお知らせはこちら
https://www.city.matsudo.chiba.jp/kosodate/matsudodekosodate/kosodatenavi/shussanshitara/yobousessyu/shigai.html
予防接種とは
ワクチンを接種することで、特定の感染症にかかりにくくなり、万が一感染しても重症化を防ぐ効果が期待できます。
ワクチン接種は「予防接種」とも呼ばれます。
予防接種はご自身を守るだけでなく、周囲の方への感染拡大を防ぐ働きがあり、社会全体の感染予防にとって大切です。
また、公衆衛生の観点からも非常に重要な役割を担っています。
さらに2020年10月からは、ロタウイルスワクチンが定期接種に加わり、それに伴い接種スケジュールも改訂されました。
接種の計画やご不明な点がございましたら、どうぞ当院までご相談ください。
痛みを抑えた注射への取り組み
当院では、小児科学会や日本外来小児科学会の研究を参考に、できるだけ痛みを抑えた接種方法を取り入れています。スタッフ一同、事前準備を徹底し、安心して接種を受けていただけるよう努めています。接種時にはまず患部を冷やす方法を行い、さらに意識をそらす工夫やその他の工夫を組み合わせており、コロナ禍で風車は使用できなくなったものの、多くの方から「痛みが少なかった」と高く評価されています。
特に小学校低学年のお子さまからは、「いつ打ったのか分からなかった」という声も聞かれ、痛みが少ない接種として安心してご来院いただけます。
また、誤接種を防ぐため、接種部位はあらかじめ決めさせていただいております。ご事情がある場合は、事前にお知らせください。
さらに、予防接種を受けられる方は、予診票をご記入のうえご来院いただくと、院内での滞在時間を短くすることができます。どうぞご協力をお願いいたします。
定期接種と任意接種について
お子さまの予防接種には、大きく分けて「定期接種」と「任意接種」があります。
定期接種は、感染力の強い病気を防ぐことを目的に行われ、接種することで集団感染のリスクを大きく減らす効果が期待されます。各自治体が予防接種法に基づいて実施しており、国の推奨期間内であれば公費で接種可能です。
一方、任意接種は、発症しても命に関わる危険性が低い病気に対して行われます。ただし、感染すると重症化する可能性もあるため、リスクを避ける目的での接種が推奨されます。
なお、定期接種であっても国の推奨期間を過ぎて接種する場合は、任意接種扱いとなり、費用は全額自己負担となります。
不活化ワクチンと生ワクチン
不活化ワクチンは、ウイルスや細菌の毒性を取り除き、免疫をつけるために必要な成分だけで作られています。接種回数はワクチンの種類によって異なりますが、十分な免疫を得るためには複数回の接種が必要です。
一方、生ワクチンは、ウイルスや細菌の病原性を弱めたもので、弱毒化されているのが特徴です。生ワクチンには、経口で接種するものと注射で接種するものがあり、ワクチンの種類によって使い分けられています。
不活化ワクチン
- ヒブワクチン
- 4種混合ワクチン
- 日本脳炎ワクチン
- 小児用肺炎球菌ワクチン
- B型肝炎ワクチン
- 季節性インフルエンザワクチン
など
注射生ワクチン
- BCGワクチン
- 水痘ワクチン
- おたふく風邪ワクチン
- 麻しん風しん混合ワクチン
など
経口生ワクチン
- ロタウイルスワクチン
など
定期接種になったロタウイルスワクチン
ロタウイルスは、重症の胃腸炎を引き起こすウイルスです。ロタウイルスワクチンを接種することで、ロタウイルスによる入院を約70~90%減らすことができます。
初回の接種は、生後6週から生後14週6日までに受けることが可能です。2回目以降の接種は、前回接種から少なくとも27日以上間隔をあける必要があります。ロタウイルスワクチンには、2回接種タイプと3回接種タイプがあります。
なお、令和2年10月1日より、ロタウイルスワクチンは定期接種として実施されています。
接種間隔の変更
ワクチン接種の間隔に関する規定が一部変更されました。今回の変更は、異なる種類のワクチンを接種する際の間隔についてです。
なお、同じ種類の注射による生ワクチンを複数回接種する場合、接種間隔はこれまで通り27日以上空ける必要があります。この点については変更はありません。
子どもの予防注射・種類と回数及び推奨年齢
定期接種
| ロタウイルスワクチン (1価または5価) |
生後6週から接種可能 1価は計2回、5価は計3回接種 1回目接種から2回目接種から4週間以上間隔を空ける。 1価は生後24週目まで、5価は生後32週目までに完了。 |
|---|---|
| 小児用肺炎球菌ワクチン | 生後2~4カ月に3回、12~15カ月までに1回 計4回接種を推奨 |
| B型肝炎ワクチン | 生後2~3カ月に2回、7~8カ月までに1回 |
| ヒブワクチン | 生後2~4カ月に3回、12~17カ月までに1回 計4回の接種を推奨 |
| 3種混合ワクチン | DPT:百日咳・破傷風・ジフテリア |
| 4種混合ワクチン | 生後2カ月~2歳の誕生日までに計4回の接種を推奨 DPT-IPV:百日咳・破傷風・ジフテリア・ポリオ |
| 2種混合ワクチン | 11~13歳未満までに1回 DT:破傷風・ジフテリア |
| 麻しん(はしか)・ 風しん混合ワクチン(MR) |
1~2歳の誕生日前までに1回 5~7歳の誕生日前までに1回の接種を推奨 |
| 水痘(水ぼうそう)ワクチン | 生後12~15カ月に1回、その後6~12カ月空けて1回 計2回を推奨 |
| ポリオ | 生後3カ月~2歳の誕生日前までに、計4回の接種を推奨 |
| 日本脳炎ワクチン | 3歳までに2回、4歳の間に1回、9~12歳の間に1回 計4回を推奨 |
| BCGワクチン | 5~8カ月未満の間に1回の接種を推奨 |
| 子宮頸がんワクチン(HPV) | 小学校6年生の女子が対象で計3回の接種を推奨 |
※推奨される年齢を過ぎてからの接種は、任意接種となります。
任意接種
| A型肝炎ワクチン | 1歳から接種可能。 1回目~2回目は2~4週間空ける 3回目は2回目の約半年後に接種 計3回を接種 |
|---|---|
| おたふく風邪ワクチン | 1歳を過ぎたら早期に接種 2回目は5歳以上7歳未満で接種 計2回を接種 |
| インフルエンザワクチン |
生後6カ月以降の全年齢 |
保護者同伴について

お子さまが予防接種を受ける際は、原則として保護者の同伴が必要です。
ただし、保護者の同伴が難しい場合でも、お子さまの健康状態をよく把握しており、予防接種や予診票の内容について理解しているご親族の方であれば、同伴のうえ接種を受けることができます。
なお、同居のご家族や親族、祖父母の方が同伴される場合でも、予診票と市区町村発行の「予防接種委任状」が必要となります。必ずご持参ください。
市川市 予防接種に保護者が同伴できない場合