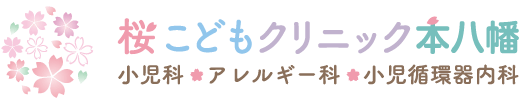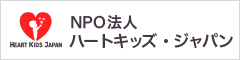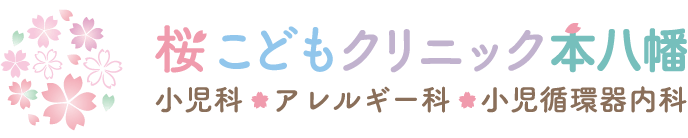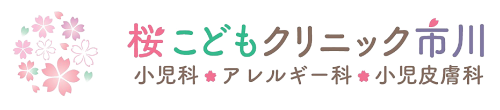爽やかな風が気持ちよい季節となりましたね。
みなさま、今年のスギ花粉はいかがでしたか。私は鼻水と目の痒み・腫れがあったので、抗ヒスタミン薬や点鼻薬などを使用しておりました。
花粉症環境保健マニュアル2022によると、花粉症の有病率は2019年に42.5%で、スギ花粉症は38.8%、ほぼ3人に1人がスギ花粉症と推定されています。
スギは日本の固有種です。
日本のスギは、ヒノキ科スギ亜科スギ属に分類される常緑針葉樹で、学名をCryptomeria japonicaといいます。
Cryptomeriaは「隠された宝」、japonicaは「日本の」という意味です。
スギの名前は直木(すぎ)に由来しており、まっすぐな木という意味です。
スギの花芽は前年の夏にでき、その後11月上旬には「休眠」という状態に入ります。
寒い冬の期間、少しずつ目覚める準備をしている花芽は、気温の上昇とともに花粉の飛散を始めます。
しかし、秋の気温が異常に高いと、休眠することなく雄花は咲いてしまうのです。
「狂い咲き」によるスギ花粉の飛散量はあまり多くありませんが、敏感な人は11月から12月頃に症状が現れます。
大昔の日本では「花粉症」はおろか「アレルギー」という病気自体が認められてはいませんでした。
そんな中、戦後アメリカ進駐軍が持ち込んだ「ブタクサ」が、その強い生命力を持って大繁殖。
1960年代に、正式に「花粉症」と認められた症状は、ブタクサの花粉症患者だったそうです。
焼け野原だった日本に、今度はビルが建つようになりました。
焼けた山々に住宅用の木材などに使うためのスギがどんどん植えられていきます。
同時に食生活は欧米的なものへと変わり、インスタント食品も増えていきます。
土だった道にはアスファルトが敷かれ、落ちた花粉は行き先を失い再び宙を舞います。
車や工場も増えたため大気が汚染され、忙しい毎日で私たちの身体の免疫バランスがおかしくなっていきます。
さらには、衛生管理が行き届くようになり、幼い頃に身につくはずだった免疫力自体が落ちるようになってきてしまいました。
そして、日本人に「国民病」と言われるほどにスギ花粉症が蔓延した背景は、以上のような経緯が考えられています。
スギ花粉症は、内服薬・点眼薬・点鼻薬を使って、治療します。
現在、「花粉の出にくいスギ」や「スギ花粉米」も新たな花粉症対策として期待されています。
当クリニックでは、今年度よりゾレアという注射での治療も導入しています。
また、スギの舌下免疫療法も行っていますが、近年、導入から1週間使用する「シダキュア2000JAU」が限定出荷となっているため、予約された方のみのご案内となっておりますので、ご了承ください。
2025年度の予約の詳細に関しては、LINEやホームページで最新の情報をお待ちください。
(スタッフJ.T)