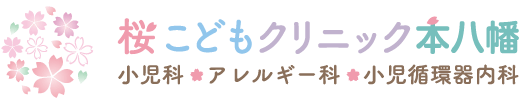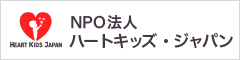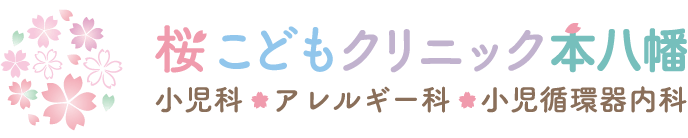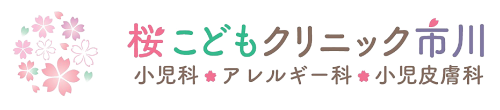小児科診療とは
お子様の発熱やのどの痛み・鼻水・鼻づまり・咳・耳の痛みなどの急性症状が見られる場合は、当院を受診してください。
お子様のつらい急性症状を少しでも早く解消するためにも、早期受診で病状の原因を見極め、さらなる長期化や悪化を予防しましょう。
お子様の治療は、服用する薬剤の種類や量・期間によって、病状が改善する効果が異なります。
当院は、すべて小児科専門医が診療しておりますので、お子様に適切な検査や治療が可能です。
また、小児科だけではなく、小児皮膚科やアレルギー科診療も行っているため、お子様の症状の内容を総合的に診断し、より適切な治療を早く行うことができます。
急性症状がある場合は、症状に応じた検査を行います。急性咽頭炎・アデノウイルス感染症・急性上気道炎・インフルエンザ・溶連菌感染症など、的確に診断と適切な治療を行います。
また、つらい症状には、呼吸器症状・皮膚症状・消化器症状にアレルギーが関わっていることも多いため、気になる症状や慢性的に症状がある場合は、お気軽に当院までご相談ください。
慢性的な咳について
 1カ月以上長期にわたって咳が続いている場合は、アレルギー疾患や何らかの感染症が考えられます。
1カ月以上長期にわたって咳が続いている場合は、アレルギー疾患や何らかの感染症が考えられます。
治療を行っても咳が治まらない場合は、服用中のお薬とこれまでの経緯から適切な診断を行うことができます。
当院を受診する際は、お薬手帳をお持ちください。また、咳症状のほかに発熱などの症状があるかどうか、同居ご家族が同じような症状があるかどうかが診断においても重要なポイントです。
当院では、丁寧に問診を行い、慢性的な咳症状の経緯をお伺いした上で必要に応じて感染症抗体価や、アレルギー検査を実施しております。
熱性痙攣(けいれん)について
 熱性痙攣(けいれん)は、乳幼児が発熱した際に起こる痙攣です。
熱性痙攣(けいれん)は、乳幼児が発熱した際に起こる痙攣です。
生後6カ月~5歳頃までのお子様に見られる症状で、ほとんどのケースでは、1~2分ほどで痙攣は治まります。
痙攣を繰り返し起こす場合や、10分以上続く場合は救急車を呼んでください。
なお、親や兄弟などの家族に熱性痙攣の経験がある場合は、熱性痙攣を起こす可能性が高いなど、遺伝的要因が考えられます。
熱性痙攣を起こしてすぐに治まった場合でも、念のため医療機関を受診してください。
嘔吐
 嘔吐を繰り返して胃の内容物が外に出た場合、こまめに水分補給を行わないと脱水する恐れがあるため、注意が必要です。
嘔吐を繰り返して胃の内容物が外に出た場合、こまめに水分補給を行わないと脱水する恐れがあるため、注意が必要です。
お子様の様子を観察し、嘔吐症状のほかに発熱や下痢症状がある場合は、速やかに医療機関を受診してください。
嘔吐は、お子様の状態をよく見極めて、適切な診断と処置が必要です。
特に、嘔吐してぐったりした様子や、顔色が悪いなどの場合には速やかに受診してください。
慢性的な下痢
 急性胃腸炎やウイルス性が原因で起こる下痢症状は、ほとんどのケースが4~5日ほどで改善します。
急性胃腸炎やウイルス性が原因で起こる下痢症状は、ほとんどのケースが4~5日ほどで改善します。
ただし、食事や水分補給に問題がなく元気なのに、1日で5~10回の下痢症状が1週間以上続いている場合は、医療機関を受診してください。
慢性的な下痢症状がある場合は、適切な診断と治療が必要です。
当院では、丁寧に問診を行い、必要に応じて腹部エコー検査やアレルギー検査を行います。受診時には、お薬手帳をお持ちください。
血便
 お子様に血便が見られた場合は、血便のほかに発熱や下痢症状の有無・お子様の機嫌が良いか悪いかなどが診断の大きなポイントとなります。
お子様に血便が見られた場合は、血便のほかに発熱や下痢症状の有無・お子様の機嫌が良いか悪いかなどが診断の大きなポイントとなります。
乳児の場合は、血便のついたオムツをお持ちいただくか、写真に撮って診察時に提示してください。
血便には、便に血液が混じっている・便全体が赤黒い・ドロっとした粘血便・黒いベタベタした血便など様々な便があります。
場合によっては、腸重積などの重篤な疾患の可能性があるため、当院では必要に応じて腹部エコー検査を行い、適切な診断と治療を行っております。
夜尿症
 夜尿症はおねしょのことを指します。ほとんどのケースで、年齢が上がるにつれておねしょの頻度が低くなります。
夜尿症はおねしょのことを指します。ほとんどのケースで、年齢が上がるにつれておねしょの頻度が低くなります。
その時期は個人によって異なりますが、5歳以上の場合が夜尿症であると基準があるため、5歳以上でおねしょの症状がある場合は早めに当院までご相談ください。夜尿症は、何らかの疾患が関与している場合もあるため、しっかりとその原因を見極めることが重要となります。
また、お子様の夜尿症は、生活の仕方やご家族の対応などで症状が改善することがあります。夕食や水分の摂り方など日中の過ごし方を改善しても症状が繰り返される場合は、腹部エコー検査や尿検査を行い、原因を特定していきます。
この場合、尿路感染症の既往症があったり、便秘だったりなど、尿や便におけるトラブルがあるかどうかも診断の重要なポイントとなります。主な治療は、アラーム療法・内服治療・お泊りの対策などを行います。夜尿症の治療においては、お子様の気持ちを大切にしながら、ご家族の協力も不可欠です。
どんな些細なことでも構いませんので、どうぞ当院まで遠慮なくご相談ください。
低身長・体重増加不良
 お子様の成長発達において、言葉の遅れや聴覚・視覚の異常・低身長・体重増加不良などの、発達の遅れに早く気付くためにも、1歳以上の健診は非常に大切です。1歳半や3歳児健診など、この時期の健診で発見し適切に診断されることで、早く対策を取ることが可能になります。
お子様の成長発達において、言葉の遅れや聴覚・視覚の異常・低身長・体重増加不良などの、発達の遅れに早く気付くためにも、1歳以上の健診は非常に大切です。1歳半や3歳児健診など、この時期の健診で発見し適切に診断されることで、早く対策を取ることが可能になります。
当院では、必要に応じて連携する高度医療機関をご紹介しております。
お子様の成長発達に心配や不安がある場合は、どうぞお気軽に当院までご相談ください。
臍ヘルニア
臍ヘルニアは「さいへるにあ」と読みます。
臍ヘルニアとは、赤ちゃんのおへそが前に盛り上がっている状態を指し、いわゆる「でべそ」のことを言います。
おへそのあたりから腸が押し出されることにより、ぽっこりとした膨らみができます。
たいていは生後1〜2か月頃に発見されることが多いです。
赤ちゃんの泣き声やいきむ動作によって、おへその膨らみがさらに目立つことがあります。

臍ヘルニアの原因
赤ちゃんはお母さんのおなかの中にいる時はへその緒で繋がっています。
出生後にへその緒が切られ、へその緒の通り道が自然にふさがっていきます。
臍ヘルニアは胎児期にへその緒が通っていた部分の筋肉が未発達によりへその緒の通り道がふさぎ切らず、腸の一部が体の外にぽこっと出てしまうことで起こります。
特に生まれて間もない赤ちゃんは、腹筋が弱くおへその部分の筋肉が完全に閉じるまでに時間がかかり、腸が体の外に押し出されやすい傾向にあります。
臍ヘルニアの症状
おへそがぽこっと体の外に膨らむような形になる状態が見られるのが特徴です。
指で押すとグジュグジュした感じで一時的に元に戻ります。
しかし、泣いたり怒ったりすることでお腹に力がかかると、おへそが飛び出してきます。
治療方法
お子さんの成長とともに腹筋も発達してくるため、自然と閉じることが多いです。
1歳までに約8割のお子さんが目立たなくなると言われていますが、おへその周りの皮膚が伸びてしまい本来のおへその形と異なる形になってしまうこともあります。
そのため、当院では、綿球とテープを使って飛び出ている腸を体の内側に押し込む「圧迫療法」を行っています。
圧迫療法はできるだけ早い段階で治療を開始するほど治癒率が高いと言われています。
一方で、生後6か月を過ぎると治療を行っても効果が低くなる傾向にあります。
そのため、生後1-2か月で小児科へのご相談がおすすめです。
また、1歳半を過ぎても臍ヘルニアの症状が残っている場合は専門の医療機関で手術が必要になることもあります。
ホームケア
綿球を固定するテープは肌に影響の少ないテープを使って治療していきますが、長期間貼ったままにしていると、皮膚が炎症を起こしてしまうこともあります。交換や外来通院についても、ご相談しながら治療をすすめて参りましょう。
お困りの方は当院にご相談ください。
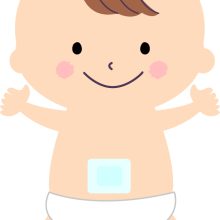
臍ヘルニアかなと思ったら
たいていは1ヵ月健診や3・4か月健診などの乳幼児健診時に指摘されることが多いですが、赤ちゃんのおへその部分がぼこっと膨らんでいることに気づいたらすぐに小児科を受診することをおすすめします。